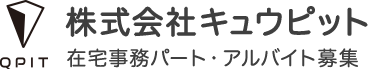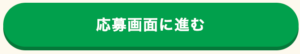家事育児を両立する最強のコツ10選!ワーママでも笑顔で過ごす秘訣

毎日時間に追われ、家事と育児の両立に悩んでいませんか?
この記事では、忙しいワーママでも実践できる、時間管理術、家族との協力体制の築き方、便利な家電や外部サービスの活用法、そして「完璧じゃなくていい」という心の持ち方まで、両立を叶える具体的な10個のコツを詳しく解説します。
無理なく笑顔で過ごすためのヒントを見つけ、あなたと家族に合った「我が家の最適解」を見つける第一歩にしてください。
家事育児の両立が難しいと感じるあなたへ
毎日、仕事に家事に育児にと、本当にめまぐるしい日々を送られていることと思います。
「もう限界かも…」「どうして私ばかりこんなに大変なの?」そんな風に、家事と育児の両立に難しさを感じて、ため息をついてしまう瞬間はありませんか?
時間にも心にも余裕がなくなり、笑顔でいることすら難しくなってしまう…それは決してあなただけではありません。多くの働くお母さん、そして家庭を支える方々が、同じような悩みを抱えています。
この章では、まずなぜ家事育児の両立がこれほどまでに難しく感じられるのか、その背景にある「壁」について一緒に考え、そして、これからご紹介する具体的なコツを実践する前に、ぜひ持っておいていただきたい大切な「心構え」についてお伝えします。
ワーママが直面する時間と心の壁
ワーキングマザー、いわゆる「ワーママ」が日々直面している現実は、想像以上に過酷なものです。
まず立ちはだかるのが、圧倒的な「時間の壁」です。
朝は子供を起こし、朝食を食べさせ、自分の身支度を整え、保育園や学童に送り届け、急いで出勤。日中は仕事に集中し、終業後は息つく間もなくお迎えへ。
帰宅後は夕食の準備、食事、お風呂、寝かしつけ…と、まるで秒刻みのスケジュール。
自分の時間はもちろん、夫婦でゆっくり話す時間すら取れない、という方も少なくないでしょう。
さらに、子供の急な発熱や自身の体調不良、予期せぬ残業など、計画通りに進まないイレギュラーな事態への対応も求められます。
そして、時間的な制約と同じくらい、あるいはそれ以上に重くのしかかるのが「心の壁」です。
「母親なのだから、育児は完璧にこなすべき」「妻として、家事もきちんとやらなければ」「仕事だって手を抜きたくない」…こうした役割に対するプレッシャーや、無意識の「〜ねばならない」という思い込みが、自分自身を追い詰めてしまうことがあります。
周りのキラキラして見えるママ友やSNSの情報と自分を比べて落ち込んだり、思うように家事や育児ができない自分に罪悪感を抱いたり。
パートナーの協力が思うように得られず、孤独感や不公平感を募らせてしまう「ワンオペ育児」状態に陥ることもあります。
こうした精神的な負担が積み重なることで、心身ともに疲弊し、笑顔でいる気力さえ失ってしまうのです。
完璧じゃなくて大丈夫!頑張りすぎないマインドセット
こうした厳しい現実に立ち向かう上で、まず何よりも大切にしてほしいのが、「完璧じゃなくて大丈夫」というマインドセットです。
家事も育児も仕事も、すべてを100点満点でこなそうと頑張りすぎていませんか?
でも、考えてみてください。あなたはスーパーマンではありません。
限られた時間と体力の中で、すべてを完璧にこなすことなど、そもそも不可能なのです。
「まあ、いっか」「今日はここまでできれば十分」と、良い意味で諦めること、手放すことを意識してみましょう。
例えば、部屋が多少散らかっていても、洗濯物が少し溜まっていても、家族が健康で笑顔でいられれば、それで十分合格点です。夕食だって、毎日手作りでなくてもいい。時にはお惣菜や冷凍食品、ミールキットなどに頼ったっていいのです。
大切なのは、「完璧」を目指して自分を追い詰め、心身をすり減らしてしまうのではなく、持続可能なペースを見つけることです。
頑張り屋さんのあなただからこそ、「もっと頑張らなきゃ」と思ってしまうかもしれません。
でも、一番大切なのは、あなた自身が心身ともに健康で、笑顔でいられること。
そのためには、意識的に休息を取り、自分を労わる時間を持つことが不可欠です。「頑張りすぎない」「無理をしない」ことを自分に許可してあげてください。この「頑張りすぎないマインドセット」こそが、これから紹介する様々なコツを活かし、家事育児との両立を長期的に成功させるための土台となるのです。
家事育児両立のコツ 時間管理と効率化編
毎日時間に追われ、「今日も何もできなかった…」と落ち込んでしまうことはありませんか?特に共働き家庭やワンオペ育児の場合、限られた時間の中で家事と育児をこなすのは至難の業です。しかし、時間管理と効率化のコツを掴めば、時間に追われる感覚から解放され、心にも余裕が生まれます。ここでは、忙しい毎日を乗り切るための具体的な時間術と効率化テクニックをご紹介します。
コツ1 優先順位を明確に やることリスト活用術
「あれもこれもやらなきゃ!」と焦る気持ちは、かえって効率を下げてしまいます。まずは「今日本当にやるべきこと」を見極めることから始めましょう。完璧を目指さず、「最低限これだけできればOK」というラインを設定することが大切です。
そこでおすすめなのが「やることリスト(ToDoリスト)」の活用です。頭の中だけで管理しようとすると、抜け漏れが出たり、常にタスクに追われているような感覚になったりします。やるべきことを書き出して可視化することで、頭が整理され、達成感も得やすくなります。
リスト作成のポイントは、タスクを細分化し、具体的な行動レベルまで落とし込むことです。「買い物」ではなく「牛乳と卵を買う」、「掃除」ではなく「リビングに掃除機をかける」のように具体的に書くと、行動に移しやすくなります。さらに、「緊急度」と「重要度」でタスクを分類するのも効果的です。「今日必ずやること」「週末にやること」「時間があればやること」などに分けて、優先順位の高いものから取り組むようにしましょう。手帳やノートに書き出すのはもちろん、スマートフォンのアプリを活用するのも便利です。
コツ2 スキマ時間を有効活用する時短家事テクニック
まとまった家事の時間が取れなくても、諦める必要はありません。日常の中には、意識すれば活用できる「スキマ時間」がたくさん隠れています。例えば、通勤電車の待ち時間、お湯が沸くまでの数分間、子どもが一人で遊んでいる時間、テレビのCM中など、5分、10分といった短い時間でも、積み重なれば大きな力になります。
このスキマ時間に、サッとできる小さな家事を組み込んでみましょう。「洗濯物をたたむ」「食卓を拭く」「明日の献立を考える」「ネットスーパーで注文する」「郵便物を仕分ける」など、短時間で完結するタスクは意外と多いものです。「チリも積もれば山となる」の言葉通り、スキマ時間を活用することで、後でまとめて家事をする負担を減らすことができます。
朝のルーティンで時短を実現
一日の始まりである朝の時間を制することは、家事育児両立の大きな鍵となります。朝の数十分を効率的に使うことで、その日一日の流れがスムーズになります。バタバタしがちな朝ですが、少し早起きして自分の時間を作る、あるいは家族が起きる前にいくつかの家事を済ませてしまうのがおすすめです。
例えば、夜のうちに翌朝の準備をしておくだけでも、朝の負担は大きく減ります。お弁当のおかずを作り置きしておく、朝食の準備(お米を研いでおく、パンとジャムを出しておくなど)をしておく、着ていく服を選んでおく、などが考えられます。また、洗濯機のタイマー機能を活用して朝起きたら洗濯が終わっているようにする、簡単な拭き掃除や片付けを朝のルーティンに組み込むのも良いでしょう。家族それぞれの朝の支度をルーティン化し、協力して行う体制を作ることも時短につながります。
夜のながら家事で効率アップ
一日の終わりに、疲れた体で家事に向き合うのは大変です。そこでおすすめなのが、リラックスタイムや他の作業と並行して行う「ながら家事」です。家事のためだけに時間を割くのではなく、他のことをしながら「ついでに」こなすことで、効率的にタスクを片付けられます。
例えば、テレビを見ながら洗濯物をたたんだり、アイロンをかけたりするのは定番のながら家事です。料理をしながらシンク周りをサッと掃除する、お風呂のお湯がたまる間に浴室を軽く掃除する、歯磨きをしながら洗面台の鏡を拭く、といったことも可能です。ただし、無理は禁物です。あくまでリラックスタイムを妨げない範囲で、負担にならない程度の家事を取り入れるようにしましょう。ながら家事を習慣化することで、家事の負担感を軽減することができます。
コツ3 家事動線を見直して無駄をなくす
毎日繰り返す家事だからこそ、その「動き=動線」に無駄があると、時間も体力も余計に消耗してしまいます。家事動線とは、家事をする際に家の中を移動する経路のことです。この動線がスムーズかどうかで、家事の効率は大きく変わってきます。
まずは、ご自身の家事の動きを意識してみてください。「洗濯物を干すために何度も部屋を往復している」「調理器具があちこちに分散していて取り出すのに手間取る」「掃除道具が使う場所から遠い」といったことはありませんか?
家事動線を改善するポイントは、「関連する作業を近くで行う」「物の配置を見直す」「収納を工夫する」ことです。例えば、キッチンであれば、シンク・コンロ・冷蔵庫を結ぶ動線(ワークトライアングル)を短く、通りやすくする。調味料や調理器具は使う場所の近くにまとめて収納する。洗濯であれば、洗濯機、物干しスペース、たたむ場所、収納場所への動線をなるべく短く、スムーズにする。掃除であれば、各部屋に小型の掃除用具を置く、掃除機をかけるルートを決めておく、などが考えられます。「使う場所に使うものを置く」という基本原則を意識して物の配置を見直すだけでも、無駄な動きが減り、家事の時短につながります。
家事育児両立のコツ 家族との分担と協力編
家事や育児は、決してママやパパどちらか一方だけが背負うものではありません。家族というチームで協力し、支え合うことが、笑顔で毎日を過ごすための重要な鍵となります。ここでは、パートナーやお子さんと上手に家事育児を分担し、協力体制を築くための具体的なコツをご紹介します。
コツ4 パートナーとの家事育児分担を具体的に決める
パートナーとの家事育児分担は、両立生活をスムーズに進める上で欠かせません。「言わなくてもやってくれるはず」「気づいた方がやればいい」という曖昧な状態は、不満やすれ違いの原因になりがちです。まずは、家庭内にどのような家事・育児タスクがあるのかを具体的に洗い出すことから始めましょう。
タスクの「見える化」が第一歩です。掃除、洗濯、料理、ゴミ出し、買い物、子供の送り迎え、寝かしつけ、保育園や学校の準備、予防接種の予約など、思いつく限りリストアップします。次に、それぞれのタスクについて、どちらが得意か、どちらの生活リズムに合っているかなどを考慮しながら、お互いが納得できる形で分担を決めていきます。完全に平等でなくても構いません。大切なのは、双方が「これなら協力してやっていける」と感じられるバランスを見つけることです。
分担方法は家庭によって様々です。「朝食の準備はパパ、夕食の片付けはママ」「ゴミ出しはパパ、洗濯物たたみはママ」といった担当制や、「月・水・金はパパ、火・木・土はママ」といった曜日交代制など、自分たちのライフスタイルに合った方法を試してみましょう。一度決めた分担も、子供の成長や仕事の状況に合わせて、定期的に見直す柔軟性を持つことも大切です。
感謝を伝えるコミュニケーションで円満に
分担を決めたら、それを円滑に運用するために日々のコミュニケーションが不可欠です。特に重要なのが、「ありがとう」という感謝の気持ちを言葉で伝えること。「やってくれて当たり前」という態度は、相手のモチベーションを下げてしまいます。どんなに小さなことでも、相手がしてくれたことに対して「ありがとう、助かったよ」「いつもきれいにしてくれて嬉しい」など、具体的に感謝の言葉を伝えましょう。
また、相手の頑張りを認め、ねぎらいの言葉をかけることも大切です。「今日もお疲れ様」「大変だったね」といった一言があるだけで、お互いを思いやる気持ちが育まれ、協力体制がより強固になります。もし、分担通りにいかないことや改善してほしいことがあっても、感情的に責めるのではなく、「〇〇で困っているんだけど、こうしてもらえると助かるな」というように、「I(アイ)メッセージ」で具体的に、そして提案する形で伝えることを心がけましょう。良好なコミュニケーションが、円満な協力関係の土台となります。
コツ5 子供も参加できるお手伝いで自立心を育む
家事は大人の仕事と決めつけず、子供も家族の一員として参加できる機会を作ることも、家事育児の両立を助けるコツの一つです。小さいうちからお手伝いを経験することは、親の負担を少し軽くするだけでなく、子供の自立心や責任感、自己肯定感を育む上で非常に大切な経験となります。
お手伝いの内容は、子供の年齢や発達段階に合わせて、無理なくできることから始めましょう。例えば、2~3歳ならおもちゃの片付けや、洗濯物をカゴに入れること。4~5歳なら食事の配膳やテーブル拭き、自分の服をたたむこと。小学生になれば、お風呂掃除や簡単な料理の手伝い、自分の部屋の掃除なども任せられるようになるでしょう。
お手伝いを習慣化するためには、「できたら褒める」「ありがとうと感謝を伝える」ことが何よりも重要です。完璧にできなくても、まずは「やろうとしたこと」「挑戦したこと」を認め、前向きな言葉をかけましょう。「〇〇ちゃんのおかげでママ助かったよ!」といった言葉は、子供のやる気を引き出します。また、お手伝いリストを作ってシールを貼るなど、ゲーム感覚で楽しめる工夫を取り入れるのも効果的です。最初から完璧を求めず、気長に見守る姿勢で、子供の「やりたい」気持ちを育てていきましょう。家族みんなで家事に取り組む経験は、子供にとってもかけがえのない学びとなります。
家事育児両立のコツ テクノロジーと外部サービス活用編
毎日時間に追われる家事と育児。少しでも負担を軽くし、心と時間にゆとりを生み出すためには、便利なテクノロジーや外部サービスを賢く活用することが非常に効果的です。ここでは、あなたの家事育児をサポートしてくれる具体的な方法をご紹介します。
コツ6 最新時短家電を導入して家事負担を劇的に減らす
「時は金なり」ということわざがあるように、家電への初期投資は、長期的に見てあなたの貴重な時間を生み出す賢い選択です。特に共働き家庭やワンオペ育児で奮闘している方にとって、時短家電は心強い味方となるでしょう。毎日のルーティンワークとなっていた家事から解放され、子供と向き合う時間や自分のためのリフレッシュ時間を確保できます。
おすすめ便利家電 ロボット掃除機 食洗機 乾燥機付き洗濯機
数ある時短家電の中でも、特に導入効果が高いとされるのが「三種の神器」とも呼ばれるロボット掃除機、食洗機、そして乾燥機付き洗濯機です。
ロボット掃除機(例:ルンバ、ブラーバなど)
スイッチひとつ、あるいはタイマー設定しておくだけで、あなたが他の家事をしている間や外出中に床掃除を自動で行ってくれます。掃除機がけの手間が省けるだけでなく、床に物を置かなくなる習慣がつき、部屋がすっきり片付くという副次的な効果も期待できます。最近では水拭き機能付きのモデルも人気があり、より清潔な床を保てます。
食洗機(例:パナソニック、リンナイなどのビルトイン型や卓上型)
毎食後の憂鬱な食器洗いから解放されるだけでも、精神的な負担は大きく軽減されます。手洗いよりも高温のお湯で洗浄するため衛生的であり、実は手洗いよりも水道代を節約できるケースも多いです。食器をセットする手間はありますが、洗い物の時間を他の家事や子供との時間に充てられるメリットは計り知れません。
乾燥機付き洗濯機(例:パナソニック、日立、シャープなどのドラム式洗濯乾燥機)
洗濯物を干す、取り込むという一連の作業は、意外と時間と手間がかかるものです。特に雨の日や花粉の季節は外干しできず、部屋干しのスペース確保や生乾きの臭いに悩まされることも。乾燥機付き洗濯機があれば、洗濯から乾燥までノンストップで行え、天候に左右されずにいつでも洗濯物をふわふわに仕上げられます。タオル類だけでも乾燥機能を使えば、日々の負担は大きく変わるでしょう。
これらの他にも、電気圧力鍋や自動調理鍋(例:ホットクックなど)は、材料を入れてボタンを押すだけで美味しい料理が完成し、調理中の「見守り」負担を軽減してくれます。
コツ7 ネットスーパーや食材宅配サービスを賢く利用
毎日の買い物も、小さな子供を連れていたり、仕事で疲れていたりすると大きな負担になります。重い荷物を持って帰る手間や、お店での余計な買い物を防ぐためにも、オンラインサービスの活用は非常に有効です。
ネットスーパー(例:イオンネットスーパー、楽天西友ネットスーパーなど)
自宅にいながらスマートフォンやパソコンで注文でき、指定した日時に玄関先まで届けてくれる便利なサービスです。重たいお米や飲料、かさばるオムツなどを運ぶ手間が省けるのは大きなメリット。店舗での買い忘れを防いだり、予算内で計画的に購入したりするのにも役立ちます。
食材宅配サービス
毎週決まった曜日に、厳選された食材や日用品を届けてくれるサービスです。安全性に配慮した食材や、スーパーでは手に入りにくい商品を取り扱っている場合も多く、食へのこだわりがある方にも人気です。献立に悩む方向けのセットや、離乳食に便利な商品が充実しているサービスもあります。
ミールキットや作り置き惣菜も選択肢に
「毎日の献立を考えるのが大変」「料理する時間がない」という悩みには、さらに一歩進んだサービスが助けになります。
ミールキット(例:Kit Oisix、ヨシケイなど)
カット済みの食材と調味料、レシピがセットになっており、短時間で主菜・副菜が作れるのが特徴です。献立を考える手間や食材を余らせる心配がなく、料理が苦手な方でも手軽に美味しい食事を用意できます。忙しい日の夕食準備に最適です。
作り置き惣菜・冷凍弁当宅配(例:ワタミの宅食、noshなど)
温めるだけ、解凍するだけで食べられる調理済みの惣菜や弁当を届けてくれるサービスです。栄養バランスが考慮されているものが多く、疲れて何も作りたくない日の強い味方になります。冷凍庫にストックしておけば、いざという時に安心です。
これらのサービスは、それぞれ特徴や料金体系が異なります。ご自身のライフスタイルや予算、食の好みに合わせて、まずは試してみて、無理なく続けられるものを見つけることが大切です。テクノロジーと外部サービスを上手に取り入れて、家事育児の負担を賢く減らしていきましょう。
家事育児両立のコツ マインドセットとセルフケア編
毎日時間に追われ、やるべきことに忙殺される家事育児。タスクをこなすテクニックも大切ですが、それ以上にママ自身の心の持ちようや、自分を労わる時間が、笑顔で両立を続けるための鍵となります。ここでは、頑張りすぎず、自分を大切にするためのマインドセットとセルフケアのコツをご紹介します。
コツ8 完璧主義を手放す 家事は6割できればOK
「ちゃんとしなきゃ」「もっと完璧に」…真面目な方ほど、そう考えて自分を追い詰めてしまいがちです。しかし、家事も育児も、毎日100点満点を目指す必要は全くありません。むしろ、完璧を求めすぎると、できなかった時に自己嫌悪に陥ったり、イライラしてしまったりと、心に余裕がなくなってしまいます。
思い切って、「家事は6割できていれば上出来!」と考えてみませんか?例えば、洗濯物がたためていなくても、乾いていればOK。夕食がお惣菜や冷凍食品の日があってもOK。「まあ、いっか」と許せる範囲を広げることで、心の負担は驚くほど軽くなります。完璧を目指すことよりも、家族みんなが笑顔で過ごせることを優先しましょう。
コツ9 意識的に自分の時間を作りストレスを溜めない
「自分の時間なんて、とても取れない…」そう感じている方も多いかもしれません。しかし、ほんの少しの時間でも、意識的に自分のための時間を作ることは、家事育児を乗り切る上で非常に重要です。自分の時間が全くないと、ストレスが蓄積し、心身ともに疲弊してしまいます。それは結果的に、家事や育児の質にも影響を与えかねません。
大切なのは、「時間があったらやろう」ではなく、「意識して時間を作り出す」という姿勢です。たとえ5分でも10分でも構いません。自分が「ホッとする」「楽しい」と感じることをする時間を持つことで、心がリフレッシュされ、また新たな気持ちで家事育児に向き合えるようになります。
短時間でもできる気分転換方法
まとまった時間が取れなくても、日常の中でできる気分転換はたくさんあります。
- 好きな音楽を1曲だけ聴く:通勤中や家事の合間に、お気に入りの曲で気分を上げる。
- 温かい飲み物をゆっくり味わう:コーヒー、紅茶、ハーブティーなど、好きな飲み物で一息つく。
- 5分間のストレッチや深呼吸:体の緊張をほぐし、リラックス効果を得る。
- 好きな香りのアロマやハンドクリームを使う:嗅覚からリフレッシュする。
- 短い時間だけ読書や好きな動画視聴:自分の世界に少しだけ没頭する。
- ベランダや窓際で外の空気を吸う:気分転換に効果的。
大切なのは、罪悪感を持たずに「自分のための時間」を楽しむことです。自分を大切にすることが、家族を大切にすることにも繋がります。
コツ10 頼る勇気を持つ 家事代行やベビーシッターも検討
「家事も育児も、母親である自分がやらなければ」という責任感から、一人で抱え込んでしまうことはありませんか?しかし、すべてを自分一人で完璧にこなすのは不可能です。時には、周りの人やサービスに「頼る」という選択肢を持つことが、自分自身と家族を守ることに繋がります。
パートナーや両親、友人など、身近な人に頼ることはもちろんですが、家事代行サービスやベビーシッターといった外部サービスを検討するのも有効な手段です。例えば、週に1回、数時間だけ掃除や料理をお願いする、手が離せない時に子供の面倒を見てもらうなど、負担が大きい部分をプロに任せることで、時間的にも精神的にも大きな余裕が生まれます。
家事代行サービスには、「ベアーズ」や「CaSy(カジー)」、「タスカジ」など、様々な会社があります。ベビーシッターも、「キッズライン」や「ポピンズシッター」といったマッチングサービスや、お住まいの地域の「ファミリー・サポート・センター」などを活用できます。「頼ることは、決して悪いことではない」ということを心に留めておきましょう。むしろ、助けを借りて心に余裕を持つことは、より良い家庭環境を作るための賢い選択なのです。
家事育児の両立を成功させるための注意点
家事育児の両立は、日々の努力と工夫の積み重ねです。しかし、頑張りすぎて心や体が疲弊してしまっては元も子もありません。ここでは、両立生活を無理なく、笑顔で続けるために心に留めておきたい大切な注意点をご紹介します。
無理は禁物 体調管理と睡眠時間の確保を最優先に
家事も育児も仕事も、すべて完璧にこなそうとすると、あっという間にキャパオーバーになってしまいます。特にワーキングマザーは、常に時間に追われがち。体調管理と睡眠時間の確保は、忙しい毎日を乗り切るための最優先事項と考えましょう。
疲れているな、と感じたら、それは体からのSOSサインです。無理をしてしまうと、体調を崩すだけでなく、イライラしやすくなったり、判断力が鈍ったりして、かえって効率が悪くなることも。悪循環に陥る前に、意識的に休息を取りましょう。
睡眠不足は、集中力や気力の低下に直結します。「あと少しだけ」と夜更かしして家事を片付けたくなる気持ちもわかりますが、質の高い睡眠は、翌日のパフォーマンスを大きく左右します。寝る前のスマホ時間を減らす、夫婦で協力して寝かしつけの時間を確保するなど、睡眠時間を確保するための工夫を取り入れましょう。心と体の健康がすべての土台であることを忘れずに、自分自身を大切にすることを心がけてください。「今日はもう寝る!」と割り切る「やらなきゃ」を手放す勇気も時には必要です。
夫婦間のコミュニケーションを密にする
家事育児の両立は、決して一人で抱え込むものではありません。特にパートナーとの協力体制は不可欠です。そのためにも、夫婦間の密なコミュニケーションは何よりも大切になります。
「言わなくてもわかってくれるはず」という期待は、すれ違いや不満の原因になりがちです。やってほしいこと、大変だと感じていること、感謝していることなどを、具体的に言葉で伝える習慣をつけましょう。特に、感謝の気持ちを言葉で伝えることは、良好な関係を築く上で非常に重要です。「ありがとう」「助かるよ」の一言が、お互いのモチベーションを高めます。
また、家事や育児の分担についても、一度決めたら終わりではなく、子供の成長や仕事の状況に合わせて、定期的(例えば週末など)に話し合いの時間を持つことをおすすめします。お互いの状況を理解し合い、協力して乗り越えていく姿勢が、チームとしての絆を深めます。忙しい毎日の中でも、意識的に二人の時間を作り、お互いを気遣う言葉をかけ合いましょう。
他の家庭と比べすぎず我が家のペースを大切に
SNSなどを見ると、キラキラした日常や、完璧に家事育児をこなしているように見える家庭の情報が目に入ることがあります。しかし、他の家庭と比べる必要は全くありません。家族構成、働き方、子供の個性、家事の得意不得意など、家庭の状況はそれぞれ全く異なります。
他の家庭のやり方を参考にすることは良いですが、比較して落ち込んだり、焦ったりする必要はありません。「あの家はできているのに、うちは…」と考えてしまうと、自己肯定感が下がり、ストレスの原因になってしまいます。
大切なのは、「我が家にとってのベスト」を見つけることです。周りの情報に惑わされず、自分たちのペースを大切にすることを意識しましょう。完璧を目指すのではなく、「まあ、これくらいでいっか」と許容範囲を広げることも時には大切です。家族みんなが笑顔でいられる、我が家ならではの心地よいバランスを見つけていきましょう。
まとめ
家事育児の両立は多くのワーママが直面する課題ですが、工夫次第で乗り越えられます。この記事では、時間管理術、家族との協力体制の構築、ロボット掃除機やネットスーパーといった便利なテクノロジーや外部サービスの活用、そして「完璧を目指さない」マインドセットなど、具体的な10個のコツをご紹介しました。全てを一人で抱え込まず、優先順位をつけ、頼れるものを上手に使い、ご自身の心と体のケアも忘れないでください。これらのヒントを参考に、あなたらしい笑顔の毎日を見つけましょう。